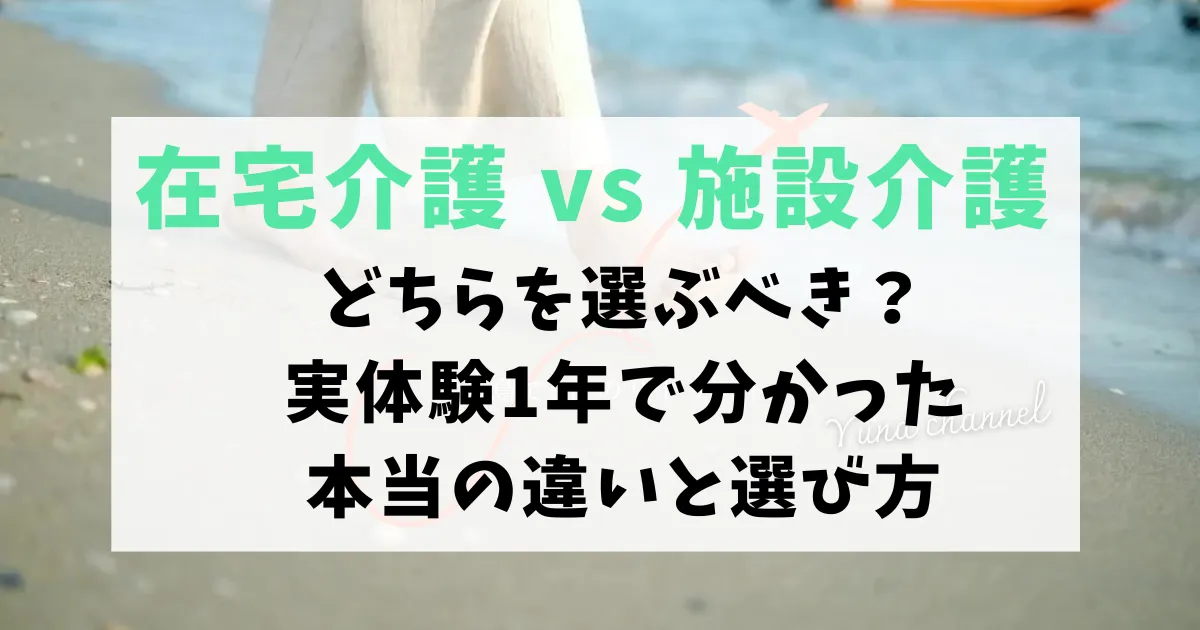こんにちは、「わたしと介護の日々」管理人の嘉陽田菜緒です。要介護2の母を自宅で介護して1年が経ちました。
「在宅介護と施設介護の違いがよく分からない」「どちらを選べばいいの?」そんな悩みを抱えていませんか?
実は私も最初は「家族だから自分で面倒を見なければ」と思い込んでいました。しかし、デイサービスのチラシをきっかけに介護保険制度を深く調べ、その結果在宅介護と施設介護の違いを理解することで、母にも私にも最適な選択ができるようになったんです。
そこでこの記事では、在宅介護と施設介護の違いを実体験を交えながら詳しく比較します。さらに、あなたの状況に合った選択ができるよう解説し、また費用面での違いや実際の体験談も含めて、具体的にお伝えしていきます。
この記事では、在宅介護と施設介護の違いを実体験を交えながら詳しく比較し、あなたの状況に合った選択ができるよう解説します。
在宅介護と施設介護の基本的な違いとは?実体験から見えた現実
まず、在宅介護と施設介護の基本的な違いを整理しましょう。私が実際に体験して分かったリアルな違いをお伝えします。
在宅介護と施設介護の定義と特徴の違い
| 項目 | 在宅介護 | 施設介護 |
| 介護場所 | 自宅(慣れ親しんだ環境) | 介護施設(専門的な環境) |
| 主な介護者 | 家族+訪問サービス | 専門スタッフ |
| 生活リズム | 本人のペースに合わせやすい | 施設のスケジュールに従う |
| プライバシー | 完全に確保される | 共同生活のため制限あり |
母の場合、認知症の進行で夜中に起きることが多くなりました。在宅介護では母のペースに合わせて対応できますが、私の睡眠不足は深刻でした。
在宅介護と施設介護のサービス内容の違い
- 在宅介護で利用できるサービス
- 訪問介護(ヘルパー)
- 訪問看護
- デイサービス(通所介護)
- ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具レンタル
- 施設介護で受けられるサービス
- 24時間体制の介護・看護
- 食事・入浴・排泄の全面サポート
- リハビリテーション
- レクリエーション活動
- 医療的ケア
私が最初に驚いたのは、在宅介護でも多くのサービスが利用できることでした。週3回のデイサービスを利用し始めてから、母の表情が明るくなり、私も息抜きの時間を持てるようになりました。
在宅介護と施設介護の対象者の違い
在宅介護に向いている方:
- 要介護度が比較的軽い(要支援1〜要介護3程度)
- 家族のサポートが得られる
- 住み慣れた環境での生活を希望している
- 医療的ケアの必要性が低い
施設介護を検討すべき方:
- 要介護度が重い(要介護4〜5)
- 家族の介護負担が限界に達している
- 24時間の見守りが必要
- 専門的な医療・介護ケアが必要
母は要介護2で、私がパート勤務のため日中は一人になります。最初は心配でしたが、デイサービスと訪問介護を組み合わせることで、安全に在宅介護を続けられています。
在宅介護と施設介護の費用を徹底比較!実際の家計への影響
介護選択で最も気になるのが費用の問題ですよね。私も最初は「お金がかかりすぎるのでは?」と不安でした。実際の費用を詳しく比較してみましょう。
在宅介護と施設介護の月額費用の違い
| 要介護度 | 在宅介護(月額) | 施設介護(月額) |
| 要介護1 | 3〜8万円 | 8〜15万円 |
| 要介護2 | 5〜12万円 | 10〜18万円 |
| 要介護3 | 8〜15万円 | 12〜20万円 |
| 要介護4 | 10〜18万円 | 15〜25万円 |
| 要介護5 | 12〜20万円 | 18〜30万円 |
我が家の実際の費用(要介護2の母):
- デイサービス(週3回):月額18,000円
- 訪問介護(週2回):月額12,000円
- 福祉用具レンタル:月額3,000円
- その他雑費:月額5,000円
- 合計:月額38,000円
思っていたより費用を抑えられているのが実感です。ただし、これは介護保険の自己負担1割の場合です。介護保険の負担割合や仕組みがよく分からない方は、「介護保険の仕組みってどうなってるの?初めてでもわかる完全ガイド」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
在宅介護と施設介護の隠れた費用の違い
在宅介護の隠れた費用:
- 住宅改修費(手すり設置、段差解消など)
- 光熱費の増加(暖房・冷房の使用時間延長)
- 家族の収入減(介護のための時短勤務・退職)
- 介護用品・消耗品費
施設介護の隠れた費用:
- 入居一時金(有料老人ホームの場合)
- 面会時の交通費
- 個人的な日用品・衣類費
- 理美容代・娯楽費
私の場合、パート勤務を週5日から週3日に減らしたため、月収が約8万円減少しました。これも在宅介護の隠れたコストとして考慮する必要があります。
在宅介護と施設介護の費用対効果の違い
在宅介護のメリット:
- 基本的な介護費用は施設より安い
- 必要なサービスだけを選択できる
- 家族の絆を深められる
施設介護のメリット:
- 24時間専門ケアが受けられる
- 家族の負担が大幅に軽減される
- 緊急時の対応が迅速
費用だけでなく、家族の精神的・身体的負担も考慮して選択することが重要だと実感しています。
在宅介護と施設介護のメリット・デメリット比較と選択のポイント
1年間の在宅介護経験を通じて見えてきた、それぞれのメリット・デメリットを正直にお伝えします。
在宅介護と施設介護のメリット・デメリット一覧
| 項目 | 在宅介護 | 施設介護 |
| メリット | ・慣れ親しんだ環境で生活 ・家族との時間を大切にできる ・個人のペースに合わせられる ・費用を抑えやすい | ・24時間専門ケア ・家族の負担軽減 ・緊急時対応が迅速 ・同世代との交流機会 |
| デメリット | ・家族の負担が大きい ・24時間の見守りが困難 ・孤立感を感じやすい ・緊急時の対応に不安 | ・費用が高額 ・環境変化によるストレス ・プライバシーの制限 ・面会時間の制約 |
母をデイサービスに送り出した後の静寂な家の中で、「これで良かったのかな」と悩む日もありました。でも、母が「今日は○○さんとお話しできて楽しかった」と笑顔で帰ってくる姿を見ると、在宅介護でも十分に母の QOL(生活の質)を保てていると実感します。
在宅介護と施設介護の選択で重要な判断基準の違い
🏠 在宅介護を選ぶべき状況:
- 要介護度:要支援1〜要介護3程度
- 家族状況:日中または夜間にサポートできる家族がいる
- 住環境:バリアフリー化が可能、または既に対応済み
- 本人の意思:自宅での生活を強く希望している
- 経済状況:施設入居費用の負担が困難
🏥 施設介護を検討すべき状況:
- 要介護度:要介護4〜5で常時介護が必要
- 家族状況:介護者の健康状態に問題がある
- 医療ニーズ:専門的な医療ケアが必要
- 安全面:転倒リスクが高く、24時間見守りが必要
- 家族の限界:介護疲れで共倒れの危険性がある
私が在宅介護を選択した決め手は、母が「家にいたい」と繰り返し話していたことでした。ただし、要介護度が上がったり、私の体調に問題が生じた場合は、施設介護への移行も視野に入れています。
在宅介護と施設介護の切り替えタイミングの違い
⚠️ 在宅介護から施設介護への切り替えサイン:
- 身体機能の急激な低下
- 歩行が困難になり、車椅子が必要
- 嚥下機能の低下で誤嚥リスクが高まる
- 排泄の自立が困難になる
- 認知症の進行
- 徘徊行動が頻繁になる
- 昼夜逆転が激しくなる
- 家族を認識できなくなる
- 家族の限界
- 介護者の体調不良が続く
- 仕事との両立が困難
- 精神的ストレスで日常生活に支障
実際に私も、母の夜間の徘徊が始まった時期は「このまま在宅介護を続けられるだろうか」と真剣に悩みました。ケアマネジャーさんに相談し、ショートステイを月2回利用することで、なんとか乗り切ることができています。
在宅介護と施設介護の違いに関するよくある質問
基本的な疑問について
Q1. 在宅介護と施設介護の違いは何ですか?
A. 最大の違いは介護を行う場所と主な介護者です。在宅介護は自宅で家族が中心となって介護し、必要に応じて訪問サービスを利用します。施設介護は専門施設で24時間体制の専門スタッフがケアを提供します。費用面では在宅介護の方が基本的に安く抑えられますが、家族の負担は大きくなります。
Q2. 訪問介護と施設介護の違いは何ですか?
A. 訪問介護は在宅介護の一部で、ヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を行うサービスです。施設介護は入居型で24時間ケアが受けられます。訪問介護は必要な時間だけサービスを受けられるため費用を抑えやすく、住み慣れた環境で生活を続けられるメリットがあります。
Q3. 居宅介護と施設介護の違いは何ですか?
A. 居宅介護は自宅で受ける介護サービス全般を指し、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどが含まれます。施設介護は入居して受ける介護です。居宅介護では本人のペースに合わせたケアが可能で、家族との時間も大切にできますが、24時間の見守りは困難です。
費用に関する疑問について
Q4. 在宅介護にかかる費用は月いくらですか?
A. 要介護度や利用するサービスによって大きく異なりますが、要介護2の場合で月額3〜12万円程度です。我が家では週3回のデイサービスと週2回の訪問介護で月額約4万円です。ただし、家族の収入減や住宅改修費なども考慮する必要があります。
Q5. 在宅介護と施設介護の費用差はどのくらいですか?
A. 一般的に在宅介護の方が月額5〜10万円程度安くなります。ただし、家族の収入減や隠れたコストを含めると、実質的な差は縮まる場合があります。長期的な視点で総合的に判断することが重要です。
Q6. 在宅介護のヘルパー費用はいくらですか?
A. 介護保険を利用した場合、1回(30分〜1時間)あたり自己負担1割で300〜600円程度です。週2回利用すると月額2,400〜4,800円程度になります。ただし、介護保険の支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
実践的な疑問について
Q7. 在宅介護の大変なことランキングを教えてください
A. 私の経験から上位5つをお答えします。1位:夜間の見守り・対応、2位:入浴介助の身体的負担、3位:認知症による徘徊・混乱への対応、4位:仕事との両立、5位:社会的孤立感。特に夜間対応は睡眠不足につながり、日中の活動にも影響します。
Q8. 在宅介護のデメリットは何ですか?
A. 主なデメリットは、家族の身体的・精神的負担が大きいこと、24時間の見守りが困難なこと、緊急時の対応に不安があること、社会的孤立感を感じやすいことです。また、介護者の健康状態や仕事に影響を与える可能性もあります。
Q9. 在宅介護のメリットとデメリットを教えてください
A. メリットは住み慣れた環境での生活継続、家族との絆深化、個人ペースでのケア、費用抑制です。デメリットは家族負担の増大、24時間見守りの困難、緊急時対応の不安、社会的孤立感です。どちらを重視するかは家族の価値観や状況によって異なります。
Q10. 施設から在宅へ移行する理由は何ですか?
A. 主な理由は、本人の「家に帰りたい」という強い希望、家族との時間を大切にしたい思い、施設の環境に馴染めない、費用負担の軽減などです。ただし、在宅介護体制をしっかり整えてから移行することが重要です。
特殊なケースに関する疑問について
Q11. 在宅介護で家族が限界に達した時はどうすればいいですか?
A. まずはケアマネジャーに相談し、ショートステイの利用頻度を増やす、デイサービスの回数を増やす、訪問介護の時間を延長するなどの対策を検討します。それでも限界の場合は、施設介護への移行を真剣に考える時期です。家族の健康を犠牲にしてまで続ける必要はありません。
Q12. 要介護5の在宅介護費用はどのくらいかかりますか?
A. 要介護5の場合、介護保険の支給限度額は月額約36万円で、自己負担1割なら月額3.6万円です。ただし、限度額を超えるサービス利用や、介護保険外のサービス、家族の収入減などを含めると、実質的には月額12〜20万円程度の負担になることが多いです。
Q13. 一人暮らしでの在宅介護は可能ですか?
A. 要介護度が軽く、認知症の症状が軽微であれば可能ですが、安全面での配慮が必要です。見守りサービス、配食サービス、緊急通報システムなどを組み合わせ、近隣や親族のサポート体制を整えることが重要です。要介護3以上では24時間対応が困難なため、施設介護を検討することをお勧めします。
Q14. ケアマネジャーとケアマネージャーの違いはありますか?
A. 表記の違いだけで、同じ職種を指します。正式名称は「介護支援専門員」で、ケアプランの作成や介護サービスの調整を行う専門職です。在宅介護では欠かせない存在で、私も月1回の訪問で様々な相談に乗ってもらっています。
Q15. 在宅介護と施設介護の比率はどのくらいですか?
A. 厚生労働省の統計によると、要介護認定者のうち約7割が在宅で介護を受けています。ただし、要介護度が上がるにつれて施設介護の割合が増加し、要介護5では約5割が施設介護を利用しています。高齢化の進展とともに、この比率は変化していく可能性があります。
まとめ:在宅介護と施設介護の違いを理解して最適な選択を
在宅介護と施設介護の違いを実体験を交えながら詳しく比較してきました。最後に、選択のポイントをまとめておきます。
在宅介護と施設介護の選択チェックリスト
| チェック項目 | 在宅介護向き | 施設介護向き |
| 要介護度 | 要支援1〜要介護3 | 要介護4〜5 |
| 家族のサポート体制 | 日中または夜間にサポート可能 | サポートが困難 |
| 本人の意思 | 自宅での生活を希望 | 専門ケアを希望 |
| 住環境 | バリアフリー対応済み | 改修が困難 |
| 経済状況 | 月額10万円以下を希望 | 月額15万円以上も可能 |
| 医療ニーズ | 定期通院程度 | 常時医療管理が必要 |
私が1年間の在宅介護で学んだ重要なポイント
- 🏠 在宅介護成功の秘訣
- 無理をせず、利用できるサービスは積極的に活用する
- ケアマネジャーとの密な連携を保つ
- 家族の健康管理も怠らない
- 将来の変化に備えて情報収集を続ける
- 💡 施設介護検討のタイミング
- 要介護度が4以上に上がった時
- 家族の体調に深刻な問題が生じた時
- 24時間の見守りが必要になった時
- 専門的な医療ケアが必要になった時
在宅介護を始めて1年、「完璧を求めすぎない」ことの大切さを痛感しています。母が笑顔で過ごせる時間を大切にしながら、私自身の健康も維持していく。そのバランスを保つために、介護保険サービスは本当に心強い味方です。
次のステップ:あなたに最適な介護方法を見つけるために
在宅介護と施設介護の違いを理解したら、次は具体的な行動を起こしましょう。
- 📋 今すぐできること
- 地域包括支援センターに相談する
- 要介護認定の申請を行う(未申請の場合)
- ケアマネジャーと面談してケアプランを検討する
- 近隣の介護サービス事業所を見学する
- 📞 相談先一覧
- 地域包括支援センター(介護全般の相談)
- 市区町村の介護保険課(制度に関する相談)
- 社会福祉協議会(生活全般の相談)
- かかりつけ医(医療面での相談)
介護は一人で抱え込むものではありません。私も最初は「家族だから自分で」と思っていましたが、多くの人に支えられて今があります。
あなたとご家族にとって最適な介護方法が見つかることを心から願っています。在宅介護でも施設介護でも、大切なのは本人の尊厳を保ちながら、家族全員が笑顔で過ごせることです。
このブログ「わたしと介護の日々」では、今後も実体験に基づいた情報をお届けしていきます。介護で悩んでいる方の少しでもお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
---
※この記事の情報は2025年時点のものです。介護保険制度や費用については変更される可能性がありますので、最新情報は各自治体や専門機関にご確認ください。
参考情報・関連リンク
在宅介護と施設介護について、さらに詳しい情報を得たい方は、以下の公的機関のサイトもご参照ください。
🏛️ 公的機関・制度に関する情報
- 厚生労働省 介護保険制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
介護保険制度の概要、自己負担割合、支給限度額などの最新情報 - 要介護認定について
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo.html
要介護認定の申請方法、認定基準、手続きの流れを詳しく解説
🔍 介護サービス検索・相談窓口
- 介護サービス情報公表システム
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
全国の介護サービス事業所を検索可能。事業所の詳細情報や評価も確認できます - 地域包括支援センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
お住まいの地域の相談窓口。介護保険サービスから生活全般の相談まで対応
🤝 生活支援・福祉サービス
- 全国社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/
地域の福祉サービス、生活困窮者支援、ボランティア活動などの情報 - 認知症施策・総合支援事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508.html
認知症に関する支援制度、相談窓口、家族向けの情報
また、これらの情報は定期的に更新されるため、必ず最新の情報をご確認ください。特に、介護保険制度は3年ごとに見直しが行われるため、費用や利用条件が変更される可能性があります。
最後に、介護は一人で抱え込むものではありません。ぜひこれらの公的機関を積極的に活用し、あなたとご家族にとって最適な介護方法を見つけてください。
※個人の体験談であり、すべての方に当てはまるものではありません。ご自身の状況に応じて専門家にご相談ください。